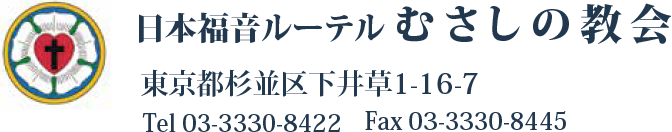Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: µŚ¦ń┤ä
-
Ķü¢ķ£ŖķÖŹĶć©ÕŠīń¼¼õĖāõĖ╗µŚźńż╝µŗØĶ¬¼µĢÖŃĆĆŃĆīÕŠōķĀåŃĆ£µ£ŹÕŠōŃü«ń¼¼õĖƵŁ®ŃĆŹŃĆĆŃĆĆÕż¦µ¤┤ ĶŁ▓µ▓╗
-
Ķ¬¼µĢÖŃĆīµŚźŃĆģµ¢░Ńü¤Ńü½ŃüĢŃéīŃü”’Į×2008Õ╣┤Ńü«ÕłØŃéüŃü½ŃĆŹÕż¦µ¤┤ĶŁ▓µ▓╗
-
Ķ¬¼µĢÖŃĆĆŃĆīµĢĄŃéƵäøŃüŚŃü¬ŃüĢŃüä’Į×ÕÆīĶ¦ŻŃü«ÕŹüÕŁŚµ×ČŃĆŹŃĆĆÕż¦µ¤┤ĶŁ▓µ▓╗
-
Ķ¬¼µĢÖŃĆīĶÖ╣Ńü«Ńé│Ńā®Ńā£Ńā¼Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│ŃĆŹŃĆĆÕż¦µ¤┤ĶŁ▓µ▓╗ńē¦ÕĖ½
-
Ķ¬¼µĢÖŃĆĆŃĆīõ║║ńö¤Ńü«ÕŹłÕŠīŃü«µÖéķ¢ōŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ŃĆŹŃĆĆÕż¦µ¤┤ĶŁ▓µ▓╗ńē¦ÕĖ½
-
Ķ¬¼µĢÖŃĆĆŃĆīµ£Ćķ½śŃü«ŃāÅŃā╝ŃāłŃāĢŃā½ŃāŚŃā¼Ńé╝Ńā│ŃāłŃĆŹŃĆĆÕż¦µ¤┤ŃĆĆĶŁ▓µ▓╗
-
Ķ¬¼µĢÖŃĆĆŃĆīõ║║ŃüŗŃéēŃü«ÕĢÅŃüäŃĆüńź×ŃüŗŃéēŃü«ńŁöŃüłŃĆŹ Ķ│ĆµØźÕæ©õĖĆ
-
Ķ¬¼µĢÖŃĆĆŃĆīõĖ╗Ńü«Ńü┐µēŗŃü«õĖŁŃü½ŃüéŃéŗĶĆģŃĆŹŃĆĆń¤│Õ▒ģµŁŻÕĘ▒