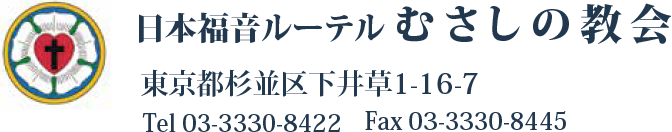Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: Ķ¬ŁµøĖõ╝ÜŃāÄŃā╝ŃāłŃĆĆĶ¬ŁµøĖõ╝ÜŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝
-
ŃĆ£Ķ¬ŁµøĖõ╝ÜŃüŗŃéēŃĆ£ ŃĆƵØæńö░µ▓ÖĶĆČķ”ÖĶæŚŃĆĆŃĆÄŃé│Ńā│ŃāōŃāŗõ║║ķ¢ōŃĆÅŃĆĆÕ╗ŻÕ╣Ė µ£ØÕŁÉ
-
’Į×Ķ¬ŁµøĖõ╝ÜŃüŗŃéē’Į× ńŠĮńö░ Õ£Łõ╗ŗĶæŚŃĆÄŃé╣Ńé»Ńā®ŃāāŃāŚŃā╗ŃéóŃā│ŃāēŃā╗ŃāōŃā½ŃāēŃĆÅ õ╗▓ÕÉē µÖ║ÕŁÉ
-
’Į×Ķ¬ŁµøĖõ╝ÜŃüŗŃéē’Į× ŃĆĆńŁÆõ║Ģ Õ║ĘķÜåĶæŚ ŃĆĵŚģŃü«Ńā®Ńā½Ńé┤ŃĆÅŃĆĆĶÅģÕĤ ńÄ▓ÕŁÉ
-
’Į×Ķ¬ŁµøĖõ╝ÜŃüŗŃéē’Į×ŃĆĆÕÅłÕÉē ńø┤µ©╣ĶæŚ ŃĆÄńü½ĶŖ▒ŃĆÅŃĆĆÕĘØõĖŖ ń»äÕż½
-
ŃĆ£Ķ¬ŁµøĖõ╝ÜŃüŗŃéēŃĆ£ ÕżÅńø«µ╝▒ń¤│ŃĆīÕÉŠĶ╝®Ńü»ńī½Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆŹ Õ╗ŻÕ╣Ė µ£ØÕŁÉ
-
Õ┐ŚĶ│Ć ńø┤ÕōēĶæŚ ŃĆÄµÜŚÕż£ĶĪīĶĘ»ŃĆÅŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕĘØõĖŖ ń»äÕż½
-
ŃĆÄń®┤ŃĆÅŃĆĆÕ░ÅÕ▒▒ńö░ µĄ®ÕŁÉŃĆĆĶæŚŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆķćÄõĖŖ ŃüŹŃéłŃü┐
-
õ║ĢŃā¬Ńā¦Ńé”ĶæŚŃĆīõĮĢ ĶĆģŃĆŹŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ õ╗ŖµØæ ĶŖÖńŠÄÕŁÉ
-
ŃāłŃā╝Ńā×Ńé╣Ńā╗Ńā×Ńā│ĶæŚ ŃĆÄŃāłŃāŗŃé¬Ńā╗Ńé»Ńā¼Ńā╝Ńé▓Ńā½ŃĆÅŃĆĆ Ķ░ĘÕÅŻ ķøģõ╗Ż
-
õĖēµĄ”ŃüŚŃüŖŃéōĶæŚ ŃĆÄĶł¤ŃéÆńĘ©ŃéĆŃĆÅ ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ ŃĆĆÕĘØõĖŖŃĆĆń»äÕż½
-
ÕĪ®ķćÄõĖāńö¤ĶæŚ ŃĆÄŃāŁŃā╝Ńā×õ║║Ńü«ńē®Ķ¬×ŃĆÅ ŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆŃĆĆ õ╗▓ÕÉēŃĆƵÖ║ÕŁÉ
-
õ║öµ£©Õ»øõ╣ŗĶæŚŃĆÄĶ”¬ķĖ×ŃĆƵ┐ĆÕŗĢńĘ©ŃĆĆõĖŖŃā╗õĖŗŃĆÅŃĆĆŃĆĆŃĆĆÕ╗ŻÕ╣ĖŃĆƵ£ØÕŁÉ